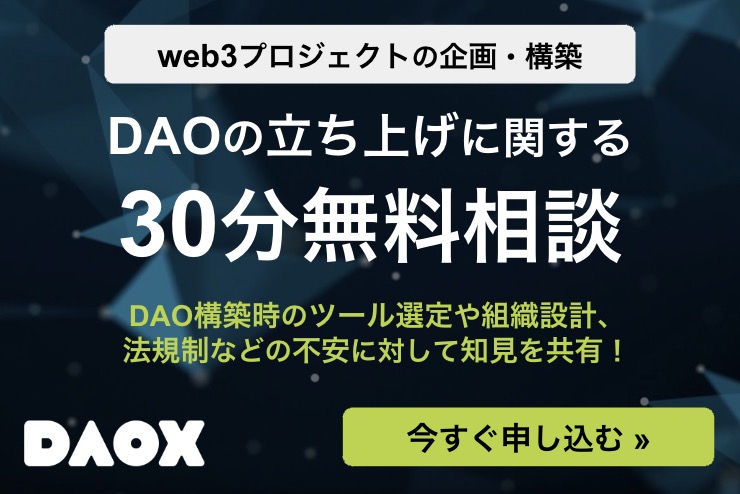近年、ブロックチェーン技術を活用したweb3が注目されるなか、環境保全への活用にも期待が高まっています。ブロックチェーン上でデジタル資産を表すNFTをCO₂削減に用いる取り組みが世界中で増えており、これらは「ReFi(Regenerative Finance)」とも呼ばれます。本記事では、NFTを使ったカーボンオフセットの仕組みや、環境保全型プロジェクトの事例を紹介。環境への取り組みを新しい形で展開したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
なお、ガイアックスでは大手企業や自治体のDAO構築を支援してきた実績をもとに、NFT/DAOのコンサルティングサービスを行っています。自社や自治体へのNFT導入を検討する際には、まず弊社資料を活用いただければ幸いです。30分のDAO導入無料相談も行っています。

NFTをどのように環境問題解決へ活用するのか
ここでは、CO₂排出削減に向けたさまざまな考え方や、NFTが環境問題の解決に貢献するしくみを解説します。カーボンニュートラルやカーボンオフセットといった基本的なキーワードに触れながら、ReFiの概要についても見ていきます。
カーボンオフセットとクレジットについて
人間の経済活動はどうしてもCO₂を排出しますが、その排出量を抑えるだけではなく、森林などによる吸収力を高める動きが「カーボンニュートラル」実現のカギとなっています。
カーボンニュートラルとは、排出量と吸収量を均衡させることで、地球全体の温室効果ガスを増やさないようにする考え方です。どうしても排出してしまうCO₂を、ほかの地域での削減・吸収活動によって埋め合わせる「カーボンオフセット」も広まりつつあります。
カーボンオフセットの一つの手段として、排出権取引の単位を「クレジット」と呼ぶことがあります。再生可能エネルギーの導入や森林管理で削減されたCO₂を定量化し、取引可能な形にしたものがクレジットです。
クレジットの透明性担保にブロックチェーンを使う
クレジットが透明性をもって取引されるためには、正確に証明できる仕組みが欠かせませんが、ここで注目されているのがNFTを活用する方法です。ブロックチェーン上に記録された情報は改ざんが困難なので、クレジットをNFT化することで透明性と信頼性の高い排出量の取引が期待できます。
こうした一連の流れを、再生的な経済活動を目指す“Regenerative Finance”、略して「ReFi」と呼ぶことがあります。ReFiはCO₂削減や環境保護を目的とした取り組みにブロックチェーン技術を用いることで、経済的メリットと環境保全を両立しようとする考え方です。
ブロックチェーンは環境に悪いのではないか
なお、そもそもブロックチェーンはマイニングなどで多くのエネルギーを消費するという指摘もありますが、近年ではFlowのようにより省エネ設計のチェーンも増えてきています。エネルギー負荷が下がれば、ブロックチェーン技術を気兼ねなく環境プロジェクトに活用できる可能性が高まります。
CO2吸収量をトークン化するReFiの例
ReFiとして運用されているweb3プロジェクトを見ると、森林の保全や植樹活動によって吸収されるCO₂量をトークン化して取引するという仕組みが多く見られます。
こうした仕組みによって、土地所有者は森林を伐採せず保全することで経済的利益を得られるようになるため、自然破壊の防止にもつながります。
NFTを活用して環境問題への取り組みを実施した事例をいくつか紹介します。
地元CO₂プロジェクト

Niterra(日本特殊陶業社)が提唱する「地元CO₂プロジェクト」は、DAO(自律分散型組織)の仕組みを活用し、地域のカーボンニュートラル化と経済循環の実現を目指すプロジェクトとなっています。
まず、“CCU”とは “Carbon dioxide Capture and Utilization” の略語で、「二酸化炭素(CO₂)を回収して、また別のかたちで活用すること」を指します。
たとえば工場で出たCO₂を集めて、ハウスみかんの光合成に役出てることで「地元CO₂で育てたみかん」ができます。
CO₂ は温室効果ガスの代表で気候変動(地球温暖化)の原因にもなるため、「できるだけ排出しない→それでも出てしまった分は回収して有効活用」という流れをめざすのがCCUの大きな狙いです。
CO₂の削減や資源循環を推進する地域の取り組みを支援し、参加者が意思決定に関わることで、持続可能な未来を共につくる仕組みを構築します。
このプロジェクトでは、コミュニティの組織形態としてDAOを導入していますので、NFT購入者がDAOのオーナーになることができ、プロジェクト成功時のリターンを得られる仕組みになっています。
Single.Earth
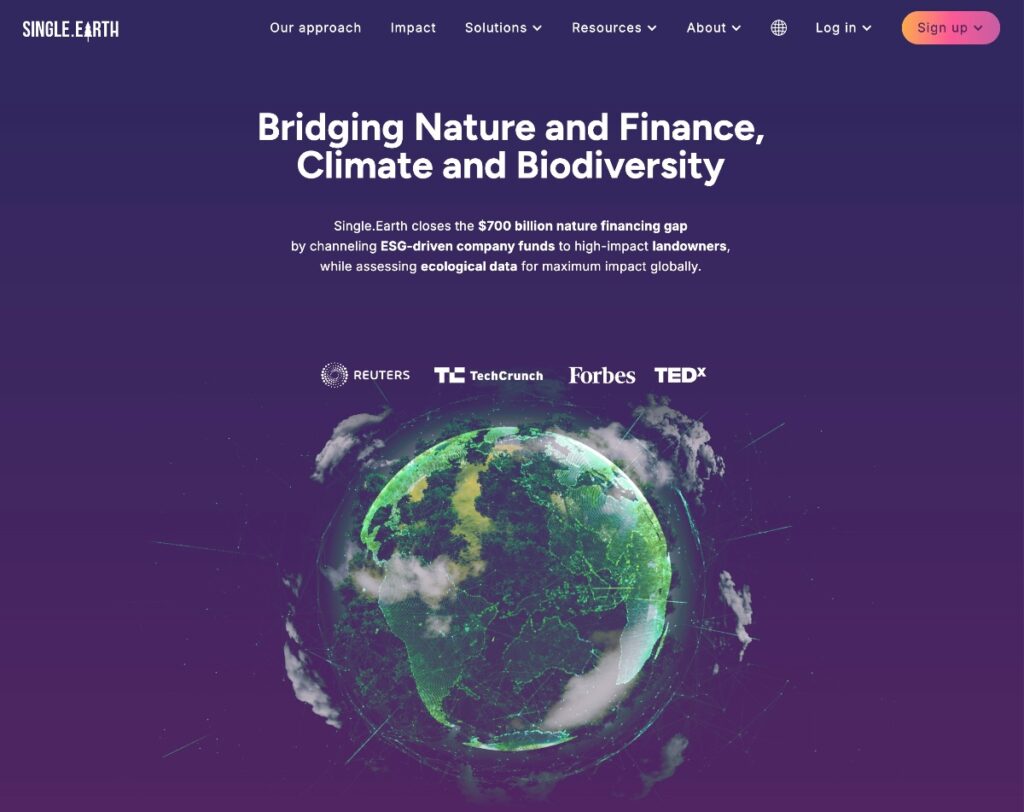
Single.Earthは、エストニアに拠点を置くグリーンテック企業で、自然資源の保護を現代経済に統合することを目指しています。
同社は、森林や湿地などの自然資源がCO₂を吸収し、生物多様性を維持する働きを「MERITトークン」としてトークン化し、土地所有者に付与する取り組みを行っています。これにより、土地をそのまま保全することが経済的なメリットにつながり、環境破壊のリスクを下げることが期待されています。
持続可能な自然保護を進める上で、経済的利益を得られるかどうかは大きなポイントですが、Single.Earthはそのギャップをブロックチェーンとトークンを使って埋めようとしています。
Coorest(クーレスト)
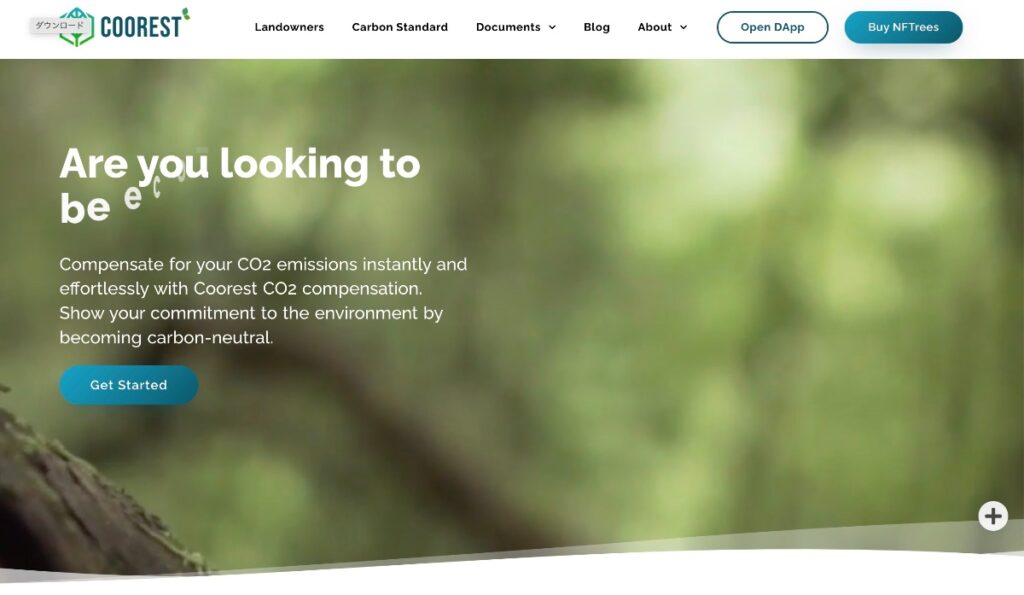
Coorestは、ブロックチェーン技術を活用して、カーボンオフセット(CO₂排出量の相殺)を透明かつ簡単に行えるプラットフォームを提供するプロジェクトです。
具体的には、実際の木を植樹し、その木が吸収するCO₂量をトークン化することで、ユーザーが自身のCO₂排出量を効果的に補償できる仕組みを構築しています。
Coorestは、実際の木と連動したNFT(非代替性トークン)である「NFTrees」を発行。ユーザーはこのNFTreeを購入・保有することで、その木が吸収するCO₂量に応じて「$CCO2」トークンを受け取ることができます。 これにより、ユーザーは自らのCO₂排出量をオフセット(相殺)することが可能です。
また、衛星データとChainlinkのオラクルを活用して、植樹された木の成長やCO₂吸収量をリアルタイムでモニタリングしています。これらのデータはブロックチェーン上に記録されるため、情報の改ざんが難しく、高い透明性と信頼性を確保しています。
このように、Coorestは、現実世界の木を植樹し、その木が吸収するCO₂量をNFTとして発行。ユーザーはNFTを購入するだけでCO₂排出量をオフセットできる仕組みになっています。植樹した木がどれだけCO₂を吸収したかといったデータがブロックチェーンに記録され、改ざんの難しい形で管理されるため、透明性のある環境貢献が可能です。
さらに、未利用地を活用して植樹し、地元の農家や地域住民を雇用することによって、経済的サポートにもつなげようとしています。このように、CO₂排出量削減だけでなく、地域の農業や雇用を支える動きも包含している点が大きな特徴です。
NFTを活用して環境保全への意識を高めるプロジェクト
NFTを用いた環境への取り組みとしては、CO₂排出を直接オフセットするだけでなく、NFTを活用して人々の意識を高めるプロジェクトも登場しています。
こうしたプロジェクトでは、寄付やイベントを通じてコミュニティ全体で環境保護を進めることが可能になっています。
PIZZA DAY
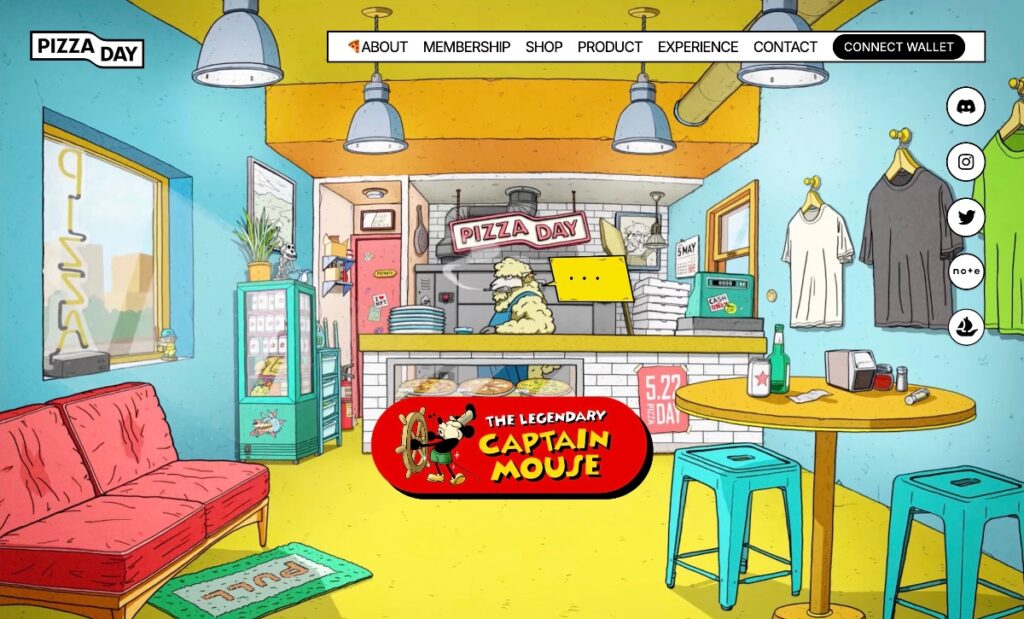
PIZZA DAYは、web3とアパレルを融合させた新しい形のブランドで、NFTを活用したデジタルメンバーシップを提供しています。 このメンバーシップを通じて、ユーザーは限定コミュニティへの参加やイベントへの優先的な招待、製品開発への参加・投票など、さまざまな特典を得られます。
環境保全の観点では、PIZZA DAYはウール素材に注目しています。ウールは100%天然繊維であり、再生可能なため、環境に優しい素材とされています。 特に、愛知県一宮市を中心とした尾州地域の高品質なウールを採用し、持続可能な素材の魅力を広めることを目指しています。
さらに、将来的には廃棄されたウール製品を回収し、肥料化することでサーキュラーエコノミー(循環型経済)の構築を目指すビジョンも掲げています。 このように、PIZZA DAYはNFTを活用したコミュニティ形成と、環境に配慮した素材選びや循環型経済の推進を通じて、持続可能な社会の実現に貢献しようとしています。
森になる猫砂プロジェクト
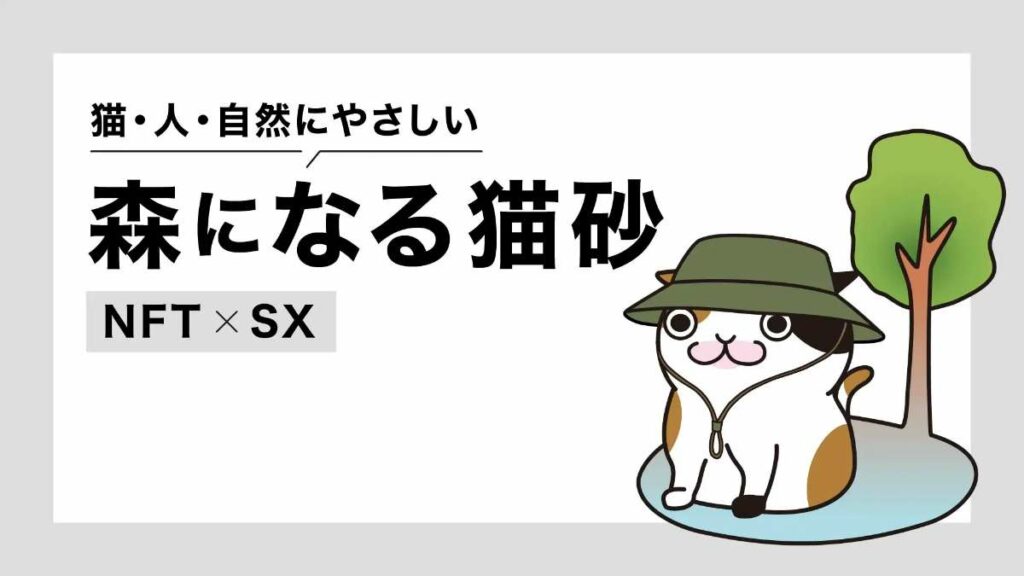
「森になる猫砂」プロジェクトは、NFTプロジェクト「Live Like A Cat(LLAC)」と株式会社UPDATERの協力により、猫や人、そして環境に優しい猫砂を提供することを目的としたプロジェクトです。
この猫砂は、宮城県栗駒山の国産木材の製材時に出る木くずを圧縮して製造され、添加物を一切使用していません。 そのため、猫や人に優しい製品となっています。
さらに、購入した猫砂と同じ量の木材を50年間育てるための資金が寄付されます。 これによって適切な伐採と再植樹を促進し、森林の健康的なサイクル維持を実現します。
また、LLACの公式オンラインショップ「またたび屋」では、対象のNFTを保有するユーザーに対して割引が適用される「NFT割引」を実施しています。 これにより、NFT保有者は特典でモチベーションを高めつつ、環境保全活動に参加できます。
DAOを活用して環境保全活動を継続させる方法
DAOを通して、複数の関係者が対等な立場で参加し、共通の目的のために資金や労力を出し合う取り組みが増えてきました。
例えば、PlanetDAOでは、日本国内の保存すべき歴史的建造物をDAOメンバーで再生して運用するといったプロジェクトになっており、海外の多くの投資家からも投資を得ています。

※PlanetDAOの場合は、NFTではなく株式会社型DAOとして株で資金調達しています。詳しくは、「日本初、”株式会社型 DAO”による歴史的建造物への小口投資プロジェクトにかけるファウンダーの想い」にて。
各個人や企業が単独で環境保全を目指すのは限界がありますし、営利企業の組織形態のなかで利益追求と環境保護をバランス良く進めるのも簡単ではありません。
DAOによって、集団の力を引き出しつつ、社会貢献にまっすぐ挑戦できることがweb3によって可能になった大きな転換点です。
これまで、web3の普及とともに多くのNFTプロジェクトが誕生しましたが、初期のものの中には「NFTを売ったら終わり」というものが多かったのも事実です。
しかし、そうではなく、NFTをミッションに共感するコミュニティの入り口とし、売上を資金調達と見てコミュニティ(=DAO)に参加したメンバーで共同運用していく。そして、掲げたミッションの達成を目指す。NFT購入者がDAOプロジェクトのオーナーとなり、成功時のリターンを得る。このようにNFTとDAOを活用すると、環境保全活動にweb3の力を用いて挑戦することができます。
ReFi関係のプロジェクトにはNFTプロジェクトとDAOまで作り込んでいるものの2種類があります。明確な線引きがあるわけではないですが、あくまで発行主体と買い手があり、オーナーは発行主体であるNFTプロジェクトと、プロジェクトの意思決定・リターン獲得権限者を参加者に譲渡し、参加者が自律的にプロジェクトを動かしていくDAOには思想の違いがあります。
NFTを売り切るだけでは環境保全につながりません。ぜひ「NFT販売の先のコミュニティ運用」まで見据えたプロジェクトの計画を行いましょう。
NFTを活用し、環境保全型のDAOを作るなら
web3による環境保護プロジェクトを立ち上げるには、NFT発行やトークンの法的な取り扱いなどの専門的なノウハウが欠かせません。
ガイアックスでは、美しい村DAOやPlanetDAO、群馬県やNitteraなどをはじめとする多くのDAO組成支援を通して培った知見を活かし、環境保全型の取り組みを支援しています。
NFTを活用してCO₂削減や自然保護を行いたい方、あるいは地方自治体と連携して新しいプロジェクトを始めたい方は、30分無料相談にお越しください。環境や地域コミュニティの課題を解決しながら、多くの人を巻き込み、長く続く活動を一緒に実現していきましょう。